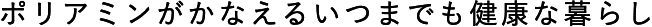目次
- 腸と脳は一心同体。腸の不調がうつ病を引き起こす原因に。
- 善玉菌の大好物、「バランスの良い食事」でうつ病を予防しよう。
- うつ病を予防する生活習慣① 食事編 4大食品を摂ることからはじめよう。
- うつ病を予防する生活習慣② 運動編 1日15分だけ運動をしてみよう。
- うつ病を予防する生活習慣③ 睡眠編ぐっすりと眠ろう!
決して甘く見てはいけない腸とうつ病の関係と、腸から考えるうつ病の予防方法を、腸の名医である消化器病専門医の江田証先生(江田クリニック院長)に教えていただきました。専門家がすすめる腸と心の健康に役立つ生活習慣を、知って、実践して、イキイキとした毎日を送りましょう!
腸と脳は一心同体。腸の不調がうつ病を引き起こす原因に。

最近、世間の注目を集めている「腸管神経」をご存知ですか? 腸には約1億個の神経細胞が存在し、その数は脳に次ぐほど。 腸のコントロールは、脳が全てを支配しているのではなく、腸自らが判断を下す機能を持っています。これがよく耳にする「第二の脳」と呼ばれる理由です。
中でも注目したいのは、脳と腸は相互に情報を発信し合っているということ。例えば、「緊張するとお腹が痛くなる」という経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。脳がストレスを感じると腸に何らかの異変が起きることがあります。その逆で、腸に何らかの不具合があると、そのストレスが脳へと伝えられ、そこから体のあらゆる場所に影響を及ぼす恐れもあります。
うつに悩む患者に、便秘や下痢が多いというデータも報告されています。人間の情緒に影響し、幸せホルモンとも呼ばれている「セロトニン」という物質は、9割が腸管でつくられます。セロトニンには腸の動きを活発にし、自律神経のバランスを整えて、心を前向きにする作用があるとされています。つまり、腸は幸福で安定した精神状態に大きく影響していると言えるでしょう。
善玉菌の大好物、「バランスの良い食事」でうつ病を予防しよう。

腸内環境に大きな影響を与えているのは「食事」です。腸に入ってきた食べものは腸内細菌のエサとなり、発酵・分解されることで体に吸収されやすい物質に変化します。この物質が食事内容によって大きく変わるため、体に影響してくるのです。
体に良い影響を与える善玉菌は、バランスの良い食事が大好物です。 特に野菜や果物が好きで、腸に入ってくると乳酸や酪酸、ビタミンB群など体にプラスに働いてくれる物質をつくり出します。
逆に体に悪影響を与える悪玉菌は、高脂質や高カロリーの偏った食事の過剰摂取が好物。便のいやなにおいの成分であるアンモニアやアミン、発がん性物質につながると言われている二次胆汁酸など、体にとってマイナスに働く物質をつくり出してしまうのです。
うつ病を予防する生活習慣① 食事編
4大食品を摂ることからはじめよう。

健康な腸=善玉菌がたくさんある状態だと思われがちですが、善玉菌の割合が悪玉菌より多いだけでは不十分です。腸内細菌の種類が多いほど、粘膜のバリア機能が高まり、外から入る細菌やウイルスに対して免疫力がアップします。腸内細菌のバリエーションを増やすためには、1日に摂る食品の数を増やすことが大切です。そして、何を食べるか、も重要です。善玉菌が育ちやすく腸の強い味方となる食品を紹介します。
| 発酵食品 | 腸内細菌の仲間である微生物が善玉菌を活性化させ、悪玉菌の増殖を抑えます。 | <主な食品> ヨーグルト ビフィズス菌や乳酸菌が含まれています。自分の腸に合うものを探してみましょう。 みそ 麹菌、酵母菌、乳酸菌の3つの善玉菌を一度に摂取でき、大豆由来の食物繊維も含まれます。 納豆 熱や胃酸に強い納豆菌は腸まで生きて届き、善玉菌を増やします。消化を助ける働きも。 |
|---|---|---|
| 水溶性食物繊維 | 水分を引きこんで便をやわらかくします。善玉菌のエサとなり、腸内バランスを整えます。 | <主な食品> 海藻 海藻のぬめり成分に食物繊維が多く含まれます。カリウムやカルシウムなどの栄養素も補うことができます。 ごぼう 食物繊維が豊富なだけでなく、善玉菌のエサになるオリゴ糖が含まれます。快便効果が期待できます。 もち麦 βグルカンという水溶性食物繊維が豊富。善玉菌を増やすだけでなく腸内の免疫力を高める効果も。 |
| オリゴ糖 | 乳酸菌のエサとなって善玉菌を増やし、腸の調子を整えます。 | <主な食品> バナナ オリゴ糖と水溶性食物繊維の両方が含まれ、便秘解消に役立ちます。 玉ねぎ がん細胞の増殖を防ぐポリフェノールが含まれます。 はちみつ 善玉菌を増やすだけでなく、酵素が消化を助けて腸の負担を軽減します。 |
| EPA・DHA | 腸の炎症を抑えて、善玉菌が増えやすい環境にします。抗酸化作用でがん予防にも効果あり。 | <主な食品> 青魚 旬のものに多く含まれます。缶詰でもOK。 さけ 抗酸化作用に腸内の炎症を抑える働きがあります。 アマニ油 αリノレン酸が胃腸の働きを活発にし、排便を促してくれます。 |
うつ病を予防する生活習慣② 運動編
1日15分だけ運動をしてみよう。

食事に加えて、運動も大切です。運動をしないと腸管の動きが悪くなります。腸のぜん動運動に変調が現れると、過敏性腸症候群を招く恐れがあり、その結果、行動意欲が生じにくくなり、うつになりやすくなってしまいます。
また、腸にとっては有害物質である便に触れる時間が長くなってしまうと、「大腸がん」のリスクも高まります。そこでおすすめしたいのが、1日15分の運動。
腸の動きを活発にするため、体の不調に合わせた運動をすることがポイントです。
不調別!おすすめの運動
<便秘気味の場合>
筋力をつけたり、早く動いたりする運動がおすすすめです。腸の振動を意識してみましょう。
スクワット
背筋はまっすぐ、腰は折らずにお尻を突き出すイメージで。また、ひざはつま先より前に出さないようにして、上げ下ろしをします。上げ下ろしは各4秒が基本です。食後や入浴後は控え、運動中に痛みを感じたらすぐに中断しましょう。
ボクササイズ
体の前でパンチを打つ構えをして、そのまま上半身を下ろします。この時90度以上ひざを曲げないようにしましょう。その体勢で、上半身をひねりながら右手で左にパンチをします。同じように、左手で右にパンチをします。これを1セット3回、1日3セット行います。
ジョギング
便秘が辛い時は、ジョギングで腸を刺激しましょう。慢性的な便秘には軽いジョギングくらいの運動が有効といわれています。
<下痢気味の場合>
体にあまり負担をかけない軽い運動がおすすすめです。少し息切れする程度がベスト。
ウォーキング
いつもより少し速度を上げて、歩幅を大きくして歩きましょう。息が軽く切れるくらいが目安です。体の水分が不足するのを避けるため、水分補給はしっかりと。
マイルドスクワット
椅子やテーブルにつかまって立ち、ひざを曲げて腰を落とします。この動作を1セット10回、1日3セット行います。ひざを曲げ、腰を落とす際は、太ももの前側の筋肉を意識しましょう。
階段上り
普段の生活の中で、エレベーターやエスカレーターではなく、階段を使うことを意識して行いましょう。
うつ病を予防する生活習慣③ 睡眠編
ぐっすりと眠ろう!

腸の仕事は、空腹時の運動、食事時の運動の主に2つです。特に重要なのが、空腹時の運動です。空腹を感じると腸が大きく収縮し、殺菌性のある消化液が腸に行き渡ります。いわば腸のおそうじ。悪玉菌を処理して腸の環境を整えてくれるのです。
腸は睡眠時にも運動しています。しかしながら、浅い睡眠では自律神経の乱れにより腸の動きを悪くしてしまうため、腸の環境を十分に整えることができなくなります。また、腸が不調の人ほど睡眠障害が多い傾向にありますので、よりよい睡眠のための習慣を見直す姿勢も大切です。
良質な腸内環境へと整える4つの睡眠習慣
就寝4時間前
食事を済ませます。睡眠時に空腹状態にすることが大切です。
就寝1時間前
就寝前に思い悩むとスムーズな入眠を妨げるため、自分を褒める習慣を付けます。
就寝中
6〜7時間の睡眠時間がベストです。毎日同じ時間帯に寝ることでリズムをつくります。
起床直後
カーテンを開けて朝日を浴びます。朝、太陽を浴びることで夜に眠りを誘発するメラトニンを生成します。
最近の研究(※1)では、腸の環境を整えておくことでストレス耐性も高まるという報告もあります。また、腸内細菌が減少すると、無感動や無感情になる恐れがあることも分かっています。
健康な心のため、毎日の充実のため、腸内環境を整えておくことは大切です。気分が落ち込む、やる気が起きないといった症状に悩まされている方は、腸内環境を悪くする生活習慣を、いま一度見直してみるのがおすすめです。
※1 Aizawa, Emiko, et al. "Possible association of Bifidobacterium and Lactobacillus in the gut microbiota of patients with major depressive disorder." Journal of affective disorders 202 (2016): 254-257.