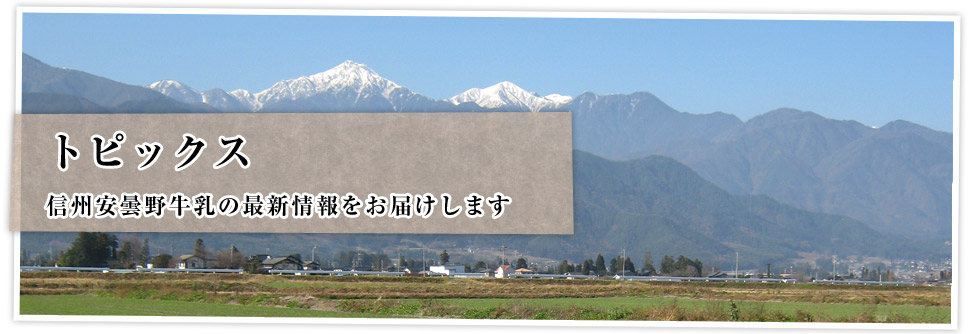
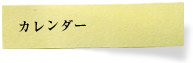
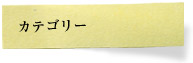
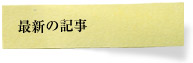
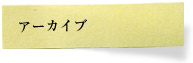
長らくお待たせいたしました。
安曇野研修報告第2弾です。
安曇野研修での2日目は、朝から甕(もたい)牧場へお邪魔し、甕さんご夫婦とそのご子息お二人、そして甕牧場の牛たちを一緒に管理している協同乳業獣医師・小池氏に酪農について、そして安曇野牛乳についてお話いただきました。
甕牧場は約2haにわたる敷地と9haに渡る牧草地で30頭弱の牛たちを育てている酪農家さんです。
甕牧場での酪農において工夫されていることは多々ありましたが、
特に印象的だった2点をご紹介したいと思います。
まずは、
◆環境のこだわり
甕牧場では、分娩前の若い牛たちは春から秋にかけて
美ヶ原という標高2000mの放牧場へ移動し高原で過ごします。
牛に新鮮な空気を吸わせ、自由に歩かせることで牛のストレスも限りなく軽減され、乳質もよくなるとのことでした。
そして言わずもがな、安曇野地域は水がとてもきれいなこと、
また6軒の酪農家さんは安曇野の狭い地域に集中しているため、
酪農家による環境のばらつきがなく、牛のストレスが少ないことも
おいしい牛乳が出る秘訣なんでしょうね。
◆エサへのこだわり
甕牧場では、自給飼料といって自分たちで飼料を作り、
それを牛たちに与えていますが、その牧草を育てるためにも堆肥が必要なので、牧場の牛たちの糞便を牧草地に使用しています。
これが飼料です。
大きい・・・!
作ったものを与え、そこからできるものでさらに作るという、
甕牧場の中で無駄のない小さな循環ができていました。
エサの種類は牧草稲わらや配合飼料、ビタミン剤など5種類くらいの餌を組み合わせているそうですが、なんと与える順番まで工夫しているとのことでした。
乳質によってその餌の種類や量を変更しながら、一定の乳質をしっかり保っているそうです。
そして牛の様子をみて(便はもちろん、なんと顔つきで具合いがわかるそうです!)、
獣医師を呼んで体調の確認するなど、とにかく"牛をよくみること"を大切にされていました。
このように、どんなに牛たちをよく見ていても、時には季節や環境の変化によって体調を崩してしまうことがあります。
そんな時は、協同乳業の獣医師たちが牧場へ駆けつけるのです。
(現在長野県内4箇所に診療所、計9名の獣医師が所属)
獣医師の基本的な業務としては、
①診療業務 ②乳質指導 ③酪農家資材及び自社乳製品の販売
④生産者団体など関係機関との連携
などがあります。
このように、メーカーと酪農家さんの架け橋の役割を担う"獣医師"の存在はとても重要であり、獣医師を配置しているメーカーは非常に珍しいです。
このような酪農家さんの努力と獣医師のサポートの甲斐もあり、
最後に、甕さんに酪農で一番大切なことを質問しました。
それは【牛への思いやり】とのことでした。
たしかに、牛が住む環境を変えてあげることも、
こだわった餌をあげることも、すべて牛たちを思ってのこと。
安曇野牛乳は、安曇野地域という恵まれた土地というだけではなく、
6軒の酪農家のみなさんと獣医師たちがそれぞれ強い思いを持ち、
苦労を重ねているからこそつくることができる牛乳なのだと改めて認識しました。
その後は売り手である販売店さんから、
お客様からもらった安曇野牛乳へのおいしいという感想や
前の記事でもご報告したご当地牛乳総選挙での5連覇の報告をし、
作り手と売り手が改めて安曇野牛乳の良さを実感するとともに、
この商品に携われる誇りと喜びを共有することができました。
最後に、甕牧場では同じ敷地でりんごを作られており、
みんなでりんご狩りを楽しみました。
安曇野地域はりんごも有名ですよね。
赤くて甘くて、その場でかぶりついて食べている販売店さんも!)^o^(
みなさん、重そうな袋を嬉しそうに抱えていました。
以上、2日間に及ぶ安曇野研修でしたが
全員無事、事故・けが等もなく、とても有意義な研修となりました。
次回は牛や安曇野牛乳に関するちょっとした小ネタやクイズなど載せる予定です!
お楽しみに(^○^)