愛されるブランドには、長年育まれてきた物語があります。
食卓に健康なおいしさをお届けする協同乳業のブランドにも、
豊かな自然の恵みを損なわずありのままに伝えたいという
多くの人々の想いが、幾重にも重なり合い綴られています。
進化し続けながらも、真に価値のあるものは大切に守り通し、
今日まで黙々と語り継がれてきた協同乳業の物語。
その1つ1つに込められた想いをシリーズでお伝えします。
協同乳業物語 03
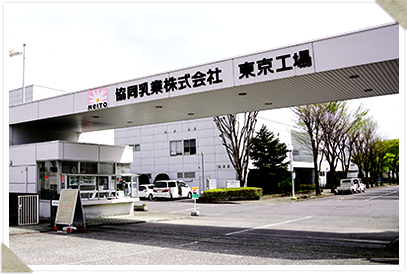
協同乳業は、自然の恵みをありのままを食卓に届けるだけでなく、健康な毎日を支える新しい提案を続ける企業である。例えば、生きて大腸まで届き、増殖するビフィズス菌"LKM512"を活用した特定保健用食品(以下、トクホ)は、協同乳業の活動を象徴するオリジナル製品だ。このような機能的な付加価値を発見し、製品に活かすための研究所が協同乳業東京工場に併設されている(1992年~)。
現在の研究所の役割は大きく次の3つである。
・腸内環境コントロール技術の開発と健康長寿の研究
・乳関連成分の新規応用技術と新製品の開発
・商品の一般分析、安全性確認、原材料分析など
その中でも、「腸内環境のコントロール技術の開発と健康長寿の研究」というテーマでは、世界的にも独自性の高い成果を上げている。



協同乳業は1980年代より自然の力を活かして健康に働きかける乳製品の開発研究を続けてきた。これまでに、日本で初めて、乳清飲料「ミルフル」を開発・発売(1984年)し、ケフィア(ヨーグルトきのこ)の工業製品化に成功するなど、乳の潜在的な力を引き出し、国民の健康促進に貢献する独自の研究開発を進めてきた。
このように健康への貢献に取り組み始めていた協同乳業は、食品による生活習慣病一次予防の重要性、科学的根拠に基づく情報を表示した食品の提供の必要性が問われ始めた1990年台、マーケティング面での要請もあり、その象徴となるような「トクホ」製品を自社ラインナップに加えるべく、社内プロジェクトをスタートさせた。
様々な健康素材が検討される中でプロジェクトは、食品から大腸内の細菌叢(さいきんそう)を整える"プロバイオティクス"という分野に着目。特に"LKM512"というビフィズス菌に見込みがありそうだというところまではコマが進んだ。
プロバイオティクスとしての有効性を検証していく中で、LKM512が、胃酸でダメージを受けずに大腸まで到達する能力が高く、さらに大腸内で増殖するという特性を持つこともわかってきた。これらのデータは、トクホ取得には必須では無かったが、作用メカニズムが解明されている食品をお客さまに提供すべきであるとの考えのもと、それらの現象も一つずつ研究し、海外学術誌に発表していった。
※LKM512・・・学名を「Bifidobacterium animalis subsp.lactis(ビフィドバクテリウム・アニマリス 亜種ラクティス)」と称するビフィズス菌の一種で、菌株名は「LKM512」
英文での論文、提出資料の作成等課題を一つ一つクリアし、「このヨーグルトは生きたビフィズス菌を含み、腸内のビフィズス菌を増やし、 腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます。」という表示が許可され、トクホ商品を発売するに至った。
社内ではトクホとして商品化出来たことにより、LKM512は研究対象としても一段落ついた感があった。しかしながら、研究員らは、被験者の便を回収し分析している過程で、LKM512を摂取することによる便状態の変化から、直感的にこの菌にはもっと秘められた可能性があるのではと考え、上司を説得しLKM512の研究を継続することとなった。また、糞便中の代謝産物を網羅的に解析するメタボロミクスに代表される、新しい技術も積極的に導入した。
研究を進める中、LKM512の持つ様々な効果を立証する論文を多数発表している(トクホ研究を始めてから、既に30報近くの科学論文を発表している)。その中でも、LKM512の長期間の投与でマウスの寿命が延伸するという世界初のプロバイオティクスによる研究成果が海外学術誌に掲載され、世間に大きなインパクトを与えることとなった。 その後も、LKM512が腸内でどのような働きをしているかを解明すべく研究を進める中、大腸内でポリアミンを増やすことにより、体内での様々な生理活性作用に影響を与えていることを見出した。
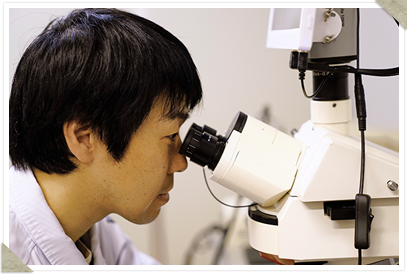
LKM512は、大腸内でポリアミンを増やし、生体に様々な効果をもたらす。協同乳業研究所は「腸内細菌に体に良いものを産生させて、健康増進を導く食品を創出する」というミッションを明確にしている。近年、アンチエイジングの分野で"ポリアミン"の機能性が大きく注目を浴びるようになっているが、このミッションの現時点での最大の成果が、このポリアミンを腸内細菌につくらせて生体に供給する技術を開発したことである。この成果で、研究員は、サイエンスの世界ではその歴史と権威で広く知られている国際的学術集会であるゴードン会議(ポリアミン)での講演を依頼されたり、ハイ・インパクトジャーナルであるScience姉妹誌『Science Advances』やNature姉妹誌 『Nature Communications』にメカニズムを解明した論文が掲載されたりするなど、世界的にも高く評価されている。すなわち、腸内細菌の産生するポリアミンの保健機能に関しては、自他共に認める先駆者且つトップランナーである。現在では、数多くの大学等の研究機関との共同研究を打診され実施しており、ポリアミンの研究成果を通して、人々の健康増進に貢献できるよう日々研究に取り組んでいる
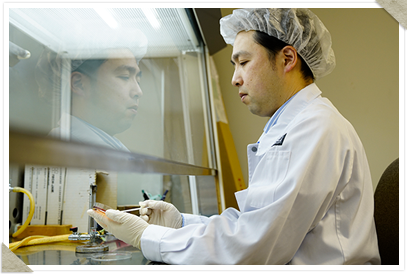


そうした研究活動の一環として位置づけられるのが、"腸内細菌に体に良いものを産生させて、健康に寄与する機能性表示食品の開発だ。 協同乳業研究所には、乳にもともと含まれている乳糖に加えて3つの難消化性成分(ガラクトオリゴ糖・マルチトール・グルコマンナン)を腸内細菌の餌として配合することで大腸内で水素ガスを発生させ、体内の不要な活性酸素を除去する乳飲料を市場に提供した実績がある。ポリアミンへの研究意欲は旺盛であり、現在も新たな機能性表示食品の開発が進められている。以下に、最近の代表例を示す。
アミノ酸の一つであるアルギニンは成長ホルモンの分泌や筋肉組織の増加効果があり、協同乳業研究所もアルギニンの摂取により多くの日本人で腸管内ポリアミンが増えることを確認していた。さらに、ポリアミンの機能研究で、ポリアミンは血管内皮細胞の健全性を維持する、すなわち血流がスムーズになって動脈硬化・心筋梗塞などの予防効果があるとの仮説を構築し、研究を進めていた。
腸内環境には個人差があるため、すべてのヒトがポリアミンを増やせるわけではない。しかし、研究チームは何度も実験を繰り返し、アルギニンとLKM512を併用摂取することで大半の日本人で腸内ポリアミンが増えることを見出し、この腸内ポリアミン産生強化技術を特許化した。さらに、このメカニズムとして、ビフィズス菌LKM512が腸内で作る酸が刺激となり、大腸菌などの一部の腸内常在菌がこの酸から身を守るため、腸に届いたアルギニンを利用して耐酸性システムを発動することに起因すること等のメカニズムを遺伝子レベルで確認した。これは学術的に重要な発見で、米国のScience姉妹誌に掲載された*1。
研究チームは、この技術を利用した実験として、肥満傾向の健常成人を2グループに分け、Aグループにビフィズス菌LKM512およびアルギニン含有ヨーグルトを、Bグループにプラセボ群(ビフィズス菌LKM512およびアルギニンを含まないヨーグルト)を12週間摂取してもらい、血管内皮機能への影響を調べた。その結果、Aグループの血管柔軟性の増加がBグループと比較して有意に高いことから、改善効果を確認した。ビフィズス菌LKM512とアルギニンを同時に体内に取り込むことで、カラダに良い物質「ポリアミン」を増やし、加齢とともに低下する血管内皮機能を改善することを証明した。*2
こうして開発された製品は、血管のしソなやかさ(柔軟性/血管を締め付けた後に開放した時の血管の拡張度)維持に役立つ機能性表示の届出が消費者庁に受理された日本初のヨーグルトとして販売されている。
*1 Kitada et al. (2018) Bioactive polyamine production by a novel hybrid system comprising multiple indigenous gut bacterial strategies.Science Advances 4(6) eaat0062.
*2 Matsumoto et al. (2019) Endothelial function is improved by inducing microbial polyamine production in the gut: A randomized placebo-controlled trial. Nutrients 11:1188.
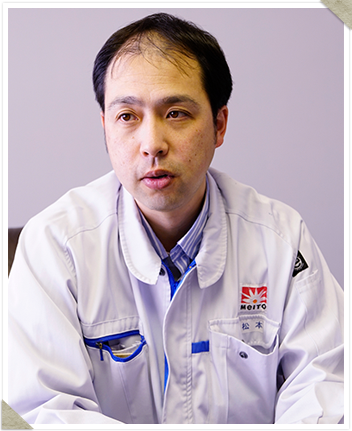
腸内菌叢は、未だ半数(8割以上ともいわれている)が未知の菌とされている。これらの菌叢が産出する物質が体内でどのような作用をするかは殆どわかっていない。
シャーレの中の細胞に対して有効だからといって、生体内で作用しているとは限らず、解明しなければならないことは山ほどある。決して、試験管やシャーレ内の実験だけで、安易に"効果がある"と発表することは決してしない。誰もやりたがらないヒトの糞便等を徹底的に解析し実験してから科学ジャーナルに発表、それが掲載されてから商品化することで、間違ったものを消費者に提供することはしない。
そうした慎重さとチャレンジ精神とのバランスの上に、独創的な技術開発を追究し続ける研究者達によって、協同乳業の製品は育まれている。